コラム
ビッグモーターによる保険金不正請求問題に端を発する一連の問題が明らかになる中で、特にそのブラックな企業体質に注目が集まっている。昨今、ブラック企業に対する世論の非難がますます高まっているにもかかわらず、なぜこのような企業体質は改善されないのか。その一つの理由として、私たちの多くが人間のできることとできないことに関して誤解しているということが挙げられる。私たちは、ひとたび崇高な理想(だと自分が思うもの)を掲げると、しばしばそれを絶対化し、その理想がどのように実現されるのかというプロセスの問題を軽視しがちである。

しかし、少し考えてみれば分かるように、人々は皆異なった考え方、嗜好、目的を持って行動しているため、全ての人々に関連するあらゆる利害関係を考慮に入れた上で、ある共通目的を打ち立てることは不可能である。無理にこれを行おうとすれば、どこかで恣意的判断が混入することは避けられず、ある種の独裁が必然となる。実際、この問題は、アメリカの経済学者であるケネス・アローが提唱した「アローの不可能性定理」として知られている(この定理は、非常に難解であるため、ここで説明することはできないが、端的に言えば、諸個人の嗜好が多様である状態の下では、社会的に最も望ましい意思決定と民主的決定が両立し得ないというものである)。
これは、いずれもノーベル経済学賞受賞者であるフリードリヒ・A・ハイエクとハーバート・A・サイモンが強調したように、人間の理性に対して過大な要求を課すことに起因している。実際、カントが『純粋理性批判』において明らかにしているように、人間の理性には限界が存在しており、私たちにとって重要なことは理性の限界を認識したうえで理性を適切に用いるということである。しかし、それにもかかわらず、私たちは常に理性を絶対化し、理性に対して過大な要求を課してしまう傾向にある。理性は一見すると常に正しい結論を導いているように思われるかもしれないが、実は同時に二律背反を生じさせてしまっている。例えば、企業利潤の最大化と従業員の賃上げはどちらも合理的に考えれば正しいものであるが、現実社会においてそれらを両立させることは困難である。
リーダーの理性過信は危険
企業の問題に戻ろう。まず、企業とはある特定の目的を達成するために意図的に創出された組織である。私たちは企業という組織の目的を達成するために、法的には平等な存在であるにもかかわらず、上司や部下という権限と命令に基づく階層化された人間関係を受け入れる。このように、上意下達のヒエラルキー的な組織構造を持つ企業は、リーダーの意思決定に従業員が従うことによって、目的を達成することができる。したがって、企業はリーダーという頭脳が命令を出し、従業員という手足がそれに従って運動するという構造を持ち、それゆえ企業の浮沈はリーダーの理性に依存するということになる。
しかし、実際の企業組織には人間関係が存在しており、リーダーが合理性を発揮することが必ずしもその目的を達成することにはつながるとは限らない。アメリカの経営学者であるチェスター・I・バーナードは、上述したような権限と命令によって特徴づけられる組織を公式組織と呼んだが、一方で、あらゆる組織には必ず権限や命令ではなく現場の人間関係に基づく非公式組織が存在し、役職とは関係ない裏のリーダーが出現することを指摘している。そして、私たちの多くはこのような役職に関係ない裏のリーダーを信頼する傾向があり、役職に基づく公式組織のリーダーにとって、組織全体を把握することが困難となる。皆さんの職場でも、役付きでないにもかかわらず、役付きの人よりも信頼されている人がいるだろう。
言い換えれば、企業組織は本来的には人間の理性によってその全貌を把握することが困難なものなのである。そのため、リーダーが自分の理性を過信し、自分の意思と組織の意思が完全に一致すると思い込んでいる場合、組織目的達成のための意思決定は恣意的なものとならざるを得ず、企業はブラック化する傾向を持つことになる。だからこそ、起業家として優れた資質を持つベンチャー企業の社長がブラックな経営を行うという例が絶えないのである。ここで重要なことは、組織はそれぞれ自らの理性を有する多数の諸個人から成り立っているという事実である。その事実を考慮することなく、リーダーが自らの理性に従業員を従わせることは先述した「アローの不可能性定理」のような問題を生じさせ、リーダーは独裁者とならざるを得ない。
人はチェスの駒ではない
実際、経済学の祖であるアダム・スミスは『道徳感情論』(1759)の中でこのように合理性を笠に着て他者を支配しようとする人々を「体系の人」として強く批判した。スミスによれば、「体系の人」は人々をチェスの駒のように考え、チェス・プレイヤーがチェスの駒を動かすことができるように、人々を動かすことができると考えている。しかし、現実においては人々はチェスの駒ではなく、それぞれの意思を持って行動する存在であるため、「体系の人」がリーダーとなった場合、その組織は独裁化するか、さもなければ大混乱のうちに崩壊することとなる。
以上より、ブラック企業の本質とは、組織が多様な諸個人によって形成される人間関係に依拠するという事実を理解せず、自らの理性を過信し、それに全ての構成員を従わせようとする「体系の人」がリーダーに就いているような組織だと言える。したがって、私たちがブラック企業という問題を乗り越えるためには、ブラック企業に対する社会的な非難だけではなく、私たち自身が日常生活において常に自らの理性の限界を鋭く自覚し、他者を自分の理性に従わせようという傲慢さを捨て去ることが不可欠となる。
実際、カントは理性の役割と限界について徹底的に考え抜いたが、彼は以下のような経験をすることで、そこに至ることができた。若き日のカントは自分が知識人であるがゆえに、知識を持たない労働者を軽蔑していたという。しかし、フランス革命に影響を与え、現代の政治哲学においても重要な存在となっているフランスの啓蒙思想家ジャン=ジャック・ルソーの思想に触れることによって、そのような自分を深く恥じ、あらゆる人々を尊敬することを学んだのである。
石井泰幸(いしい・やすゆき)
千葉商科大学サービス創造学部教授。1960年千葉県生まれ。明治大学大学院経営学研究科修士課程修了。専門が経営学、経営情報論。2008年より現職。
【転載】週刊エコノミスト Online 2023年8月1日「なぜ企業はブラック化するのか——合理性に潜むわな」石井泰幸
(https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20230801/se1/00m/020/068000d)
この記事に関するSDGs(持続可能な開発目標)

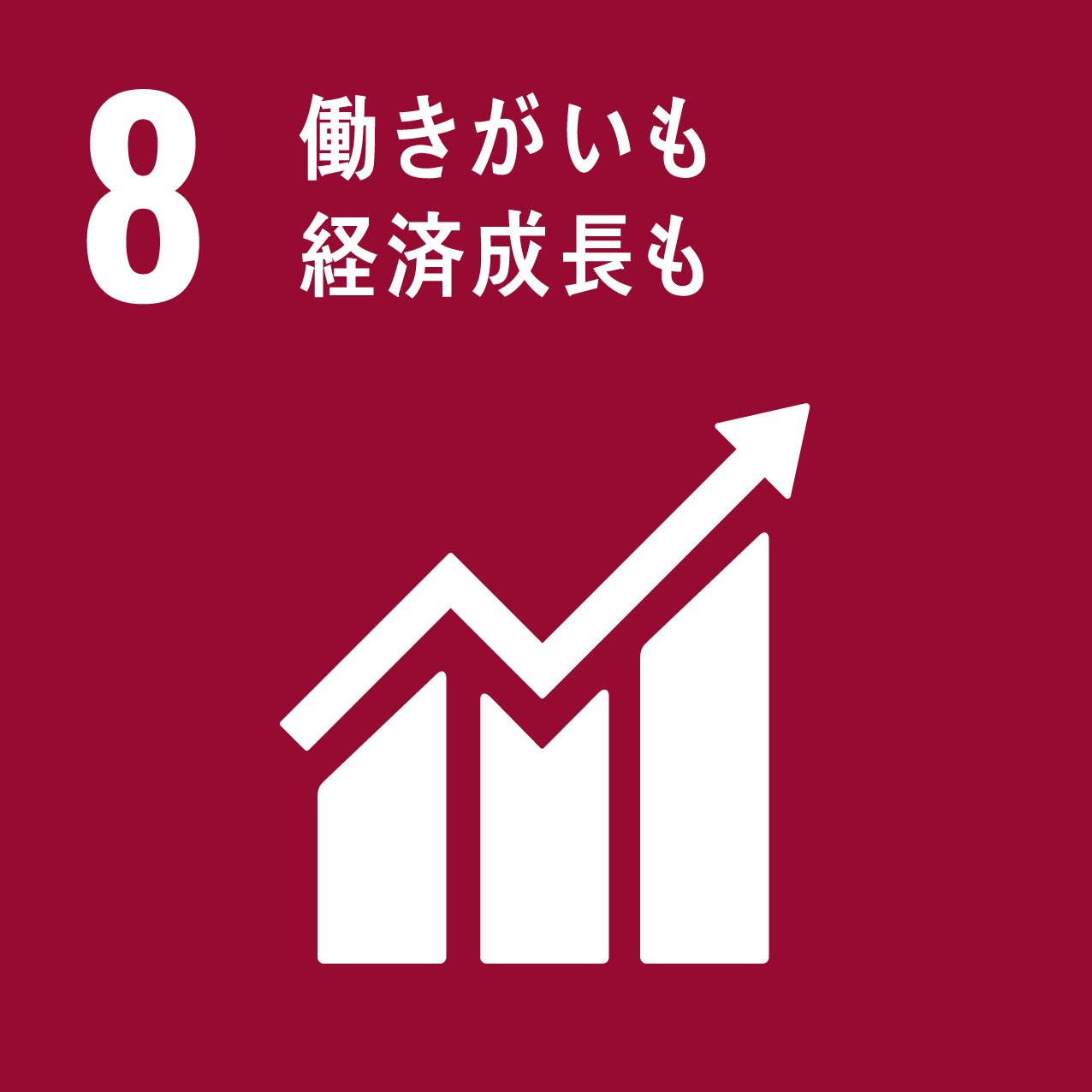

関連リンク
