2022年12月に全世界に対して一般公開されたAI(人工知能)チャットシステム「チャットGPT」が、急速に利用者を増やしている。2カ月間で利用者が1億人を超えたとの報道があり、23年1月末から2月にかけてテレビのニュースでも盛んに取り上げられた。
チャットGPTは米新興企業オープンAIが開発したもので、技術的には深層学習を用いた生成AIである。もともと英語のシステムであるにもかかわらず、日本語での質問に対しても、ほぼ自然な回答をオンラインで返すのが特長である。
世界を変えたシステムしのぐ?
私自身は1980年代初めから、機械翻訳システムのごく初期のユーザーであった。当時の機械翻訳システムは大型計算機(メインフレームコンピューター)上で稼働しており、当時最先端だった建築物構造計算プログラムと同じくらいの計算資源と計算時間が必要だった。これを使って、私の最初の翻訳出版の初稿を作ったことを覚えている。翻訳品質は貧弱で、最終稿には機械翻訳の一文も残っていなかった。それに比較すると、チャットGPTの進歩には驚かされる。
AIやICT(情報通信技術)の領域では、何度か世界を変えるシステムが発表されている。メインフレームによるビジネスを変えたIBMシステム360、電子メールが普及するきっかけとなったDARPA(米国防総省高等研究計画局)によるインターネット、音楽の携帯を可能としたソニーのウォークマン、インターネット上の情報の授受を変えた「モザイク」や「ネットスケープ」のようなウェブブラウザー、iPhoneから始まったスマートフォン、一般人の情報収集を可能としたグーグル検索エンジンなどがそれにあたる。チャットGPTはこれらのシステムをはるかにしのぐ可能性が高い。

思えば、20年ほど前に私がグーグル本社を訪問した時には、彼らは次のように話していた。「次のグーグルは必ず近いうちに出てくる。我々は次のグーグルも我が社になるように努力している」と。
グーグルが自動運転への取り組みを発表する、はるか昔のことである。チャットGPTについては、発表2カ月でマイクロソフトが製品に全面的に組み込むというし、グーグルと親会社アルファベット社は緊急事態だということで、急きょ「Bard(バード)」というAIシステムを世に出そうとしている。
ネット犯罪など「影」の懸念も
これだけ利用者と利用分野が拡大すると、当然ながら「光」と「影」に関する議論が起こっている。
光の部分については、こんな事例が挙げられる。チャットGPTは米国において一流のビジネススクールに合格する程度の回答を生成したという。私の周りでも、既にコンピュータープログラムの説明文生成や、英語論文の洗練化に利用している例がある。研究者仲間でもいろいろと試している者が多い。まじめな問題ばかりでなく、ジョーク生成のような例もある。
一方、影の部分については悲観的な予測も多い。例えば、学生・生徒がレポート作成に悪用する、ネット犯罪に利用される、人間の知性が破壊される、人類の破滅につながる、といったことだ。
それなら、チャットGPTの限界はどこにあるのだろう。基本的に生成AIは穴埋め問題を賢く解くシステムである。したがって、インターネット上に情報のない質問については、トンチンカンな回答しか作ることができない。
例えば「寺野隆雄について教えて」という日本語の質問については、「知りません。もっと追加情報をください」と答える。そこで追加質問を入力すると、まったく見当外れか、間違いだらけの回答が返る。穴埋めが得意な学生・生徒にありがちな反応である。
利用者に求められる知性
だからこそ、利用者には回答の良否を判断できるだけの知性が求められる。ちょうどNHKの人気番組「チコちゃんに叱られる!」を観ているような感じだろうか。自分が知っているテーマについては「何を知ったかぶりしているんだ」ということになるし、知らないテーマについては「いや~面白い」という反応になる。
これを読んで、チャットGPTのビジネス応用について考える読者もいるかもしれない。早速、チャットGPTに尋ねると、こんな回答があっという間に返ってくる。
「ここにいくつかのチャットGPTを利用するビジネスアイデアを紹介します。カスタマーサポートチャットボット、仮想ライティングアシスタント、万能言語翻訳、個人向けニュース要約、AI営業アシスタント。これらはビジネス環境において、チャットGPTのような言語モデルの可能性を示す数多くの提案の一部に過ぎません」。
チャットGPTはこれぐらいのことは考えている。チャットGPTを超えるビジネスを考えるのは、私たちの役割なのである。
寺野隆雄(てらの・たかお)
千葉商科大学基盤教育機構教授。1952年東京生まれ。1978年東京大学情報工学修士課程修了。1978~1989年電力中央研究所勤務。1990~2004年筑波大学。2004~2018年東京工業大学教授を経て、現職。工学博士。内外の学協会の役職経験多数。専門はシステム科学、人工知能、サービス科学など。特に企業との共同研究による先端的応用に興味をもつ。筑波大学と東京工業大学名誉教授。
【転載】週刊エコノミスト Online 2023年2月15日「チャットGPTは世界を変える」寺野隆雄
(https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20230215/se1/00m/020/006000d)
この記事に関するSDGs(持続可能な開発目標)
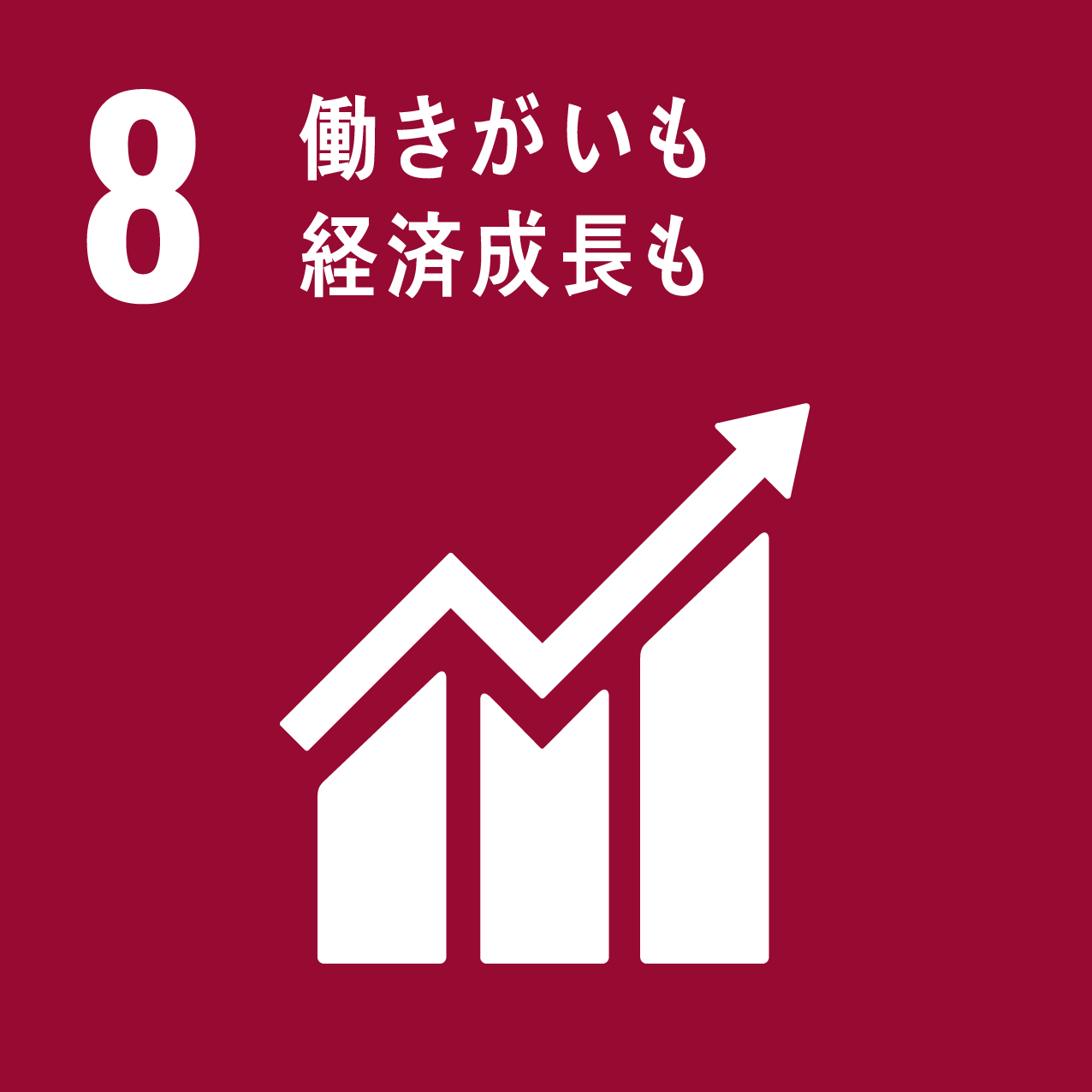


関連リンク
