コラム
今日、企業の社会的責任(Corporate Social Responsibility、以下CSR)に対して疑問を呈する人はほとんどいないであろう。CSRとは企業が事業活動において利潤追求にのみ汲々するのではなく、株主、従業員、顧客、地域住民といったステークホルダーに対して果たすべき社会的責任のことである。それはアカウンタビリティ(説明責任)、フィランソロピー(慈善事業)、環境への配慮といった形で実際に多くの企業によって実践されている。とくに、SDGs(持続可能な開発目標)がここ数年の間に一般化してからは、多く企業はCSRの具体的実践としてSDGsの達成への貢献活動にコミットメントしている。実際、ロシアによるウクライナ侵攻や気候変動等、様々な問題が顕在化する中で、企業が自らの社会的責任としてこれらの問題の解決に取り組むことは非常に重要である。
とはいえ、企業はこれらの問題に対してどこまで責任を負うべきなのか。社会的責任の範囲が曖昧であるため、このような問題が生じる。実際、私たちが日々目にしているように、CSRは法的責任よりもかなり広いものである。法的責任も当然、CSRに包含されるが、法的責任については責任の所在とその範囲が明確である点で曖昧性は存在しない。つまり、企業犯罪を行った企業は自ら行った不法行為に対して責任を負い、その責任の範囲において社会的な非難を甘受する。
不買運動のリスク
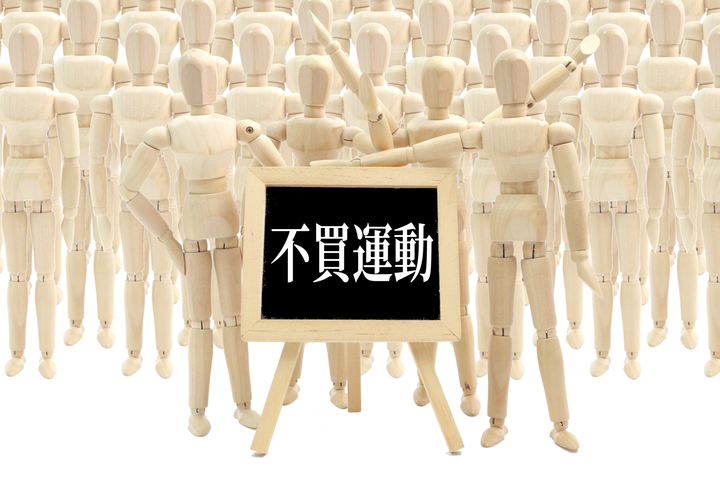
では、ある企業の行動に法的な問題がなかったとしても、倫理的に問題があった場合はどうであろうか。例えば、ある企業が自らは直接関与していなかったとしても、サプライチェーンにおいて強制労働や環境破壊があった場合である。このような事例としてアメリカの大手スポーツメーカーのナイキに対する不買運動が挙げられる。ナイキは自社製品の製造を労働費用が安価な東南アジアの工場に委託していたが、そこで児童労働が行われていたことが発覚し、世界的な不買運動を招くこととなった。ここではナイキが直接的に人権侵害行為に関わっていたわけではないが、途上国における搾取労働を助長したとして社会的な非難の対象となったのである。実際、これは適切なサプライチェーンマネジメントが行われれば、回避可能な事例であり、ナイキはマネジメントを怠ったことに対して、社会的な非難という形で責任を負うことになってしまったのである。
以上のような事例においては、企業の行為が何らかの具体的な結果を生じさせているがゆえに、企業に対して法的責任あるいは倫理的責任を追及することが可能となる。それでは、企業に抽象的な「社会的」責任を負わせることは原理的に可能なのか。「社会的」問題と私たちが言う場合、多くの場合はSDGsが掲げるような問題を意図しているであろうが、ここには企業もまた貧困の解決や気候変動対策といった問題に対して具体的なアクションを起こす義務があるという主張が多かれ少なかれ含意されている。確かに、昨今ではESG(Environment=環境、Social=社会、Governance=企業統治)投資が注目され、環境や人権に対する配慮を投資の基準としようとする動きが拡大しつつあり、企業に社会的責任を負わせることも可能になってきているようにも思われる。
しかし、企業が利潤追求を第一の目的とする組織であるという定義に立ち返れば、このような基準を経営判断の中心に据えることは企業目的と両立し得ないことは明らかである。もちろん、これは企業が法的責任、倫理的責任を果たしていることが前提の上のことであることは改めて言うまでもない。むしろ、企業の負うべき責任の範囲を過度に拡張すれば、企業がそのための行動をとることが原理的に不可能であるためにCSR自体が全く無内容な概念になるか、あるいは無理にCSRに実効性を持たせようとする結果、企業の意思決定が全て政府の監督の下に置かれることになる。
経済学者のCSR批判
とくに、後者の状況は字義通りの社会主義であり、フリードリヒ・ハイエクやミルトン・フリードマンといった経済学者はそのためにCSRを強く批判した。ハイエクやフリードマンが活躍した20世紀後半という時代はローマクラブによって『成長の限界』(1972)が出版されるなど化石燃料の枯渇、過剰人口、経済成長の限界に対する危機感が非常に高まった時代であった。このような危機感から当時の世界では、政府による資源の統制の必要性が強調されるようになったが、これは企業の本質を完全に見誤ったものである。というのは、企業の資源は意思決定の最も重要な判断材料であるため、それを政府が管理するということは意思決定の過程を全て政府にゆだねることになってしまうからである。
これは現代においても重要な問題である。というのは、企業が貧困問題や気候変動といった自らとは直接的な関係のない問題に対して責任というある種の強制に服させることがなぜ正当化されるのか、という点について十分な回答が示されていないからである。実際、たとえ国家権力による強制がなかったとしても、世論による非難という形で企業は強制を受けてしまい、自由な経済活動が不可能となってしまうのである。例えば、貧困問題について、企業はどこまでのことをすべきなのか。絶対的貧困の解決か、それとも相対的貧困まで解決すべきなのか、限られた財源において誰に対してどの程度の支援を行うべきか、またその基準は何か、企業が自らの責任において貧困救済を行うということはこのような価値判断に対しても責任を持つということである。本来、このような価値判断が許されるのは政府のみであり、それゆえ、企業が貧困問題の解決に責任を持つことは必然的に政府による企業支配へと道を開くことになる。
CSRにおける「社会的」の意味の曖昧さ
上記の問題はCSRにおける「社会的」の意味の曖昧さに起因するものである。つまり、CSRとは字義通りに解釈すれば、企業の行為の結果でない問題に対しても企業は責任を負うべきであるという信念であるが、これは明らかに企業に対する過大な要求である。企業にできることは、利潤追求において法令遵守とフェア・プレーに徹し、ステークホルダーに配慮することだけであり、貧困問題や気候変動といった抽象的な社会問題の解決に向けた根本的な行動をとることは、組織目的が利潤追求に向けられている以上、極めて困難なのである。
経済学の父であるアダム・スミスは『道徳感情論』(1759)において、「善行は建物を支える基礎ではなく、建物を飾る装飾品であって、それゆえ善行は奨励されれば十分であり、決して強制されるものではない。反対に、正義は壮大な構造物全体を支える大黒柱である。それが取り除かれれば、人間社会という巨大な構造物は……たちまち灰燼(かいじん)に帰すに違いない」と述べており、善行と正義を区別することの重要性を述べている。CSRとはまさに善行と正義の混同であり、したがって、それは自由な社会と両立が不可能な概念にもなり得るのである。だからこそ、例えばSDGsを達成するという場合には、それがその企業の真の意味での責任の範囲か否かを見極めることが自由な社会とSDGsの両立、ひいてはその企業の利潤獲得機会の拡大につながるのである。
石井泰幸(いしい・やすゆき)
千葉商科大学サービス創造学部教授。1960年千葉県生まれ。明治大学大学院経営学研究科修士課程修了。専門が経営学、経営情報論。2008年より現職。
【転載】週刊エコノミスト Online 2023年11月19日「企業の社会的責任(CSR)と利潤追求を考える」石井泰幸
(https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20231117/se1/00m/020/002000d)
この記事に関するSDGs(持続可能な開発目標)
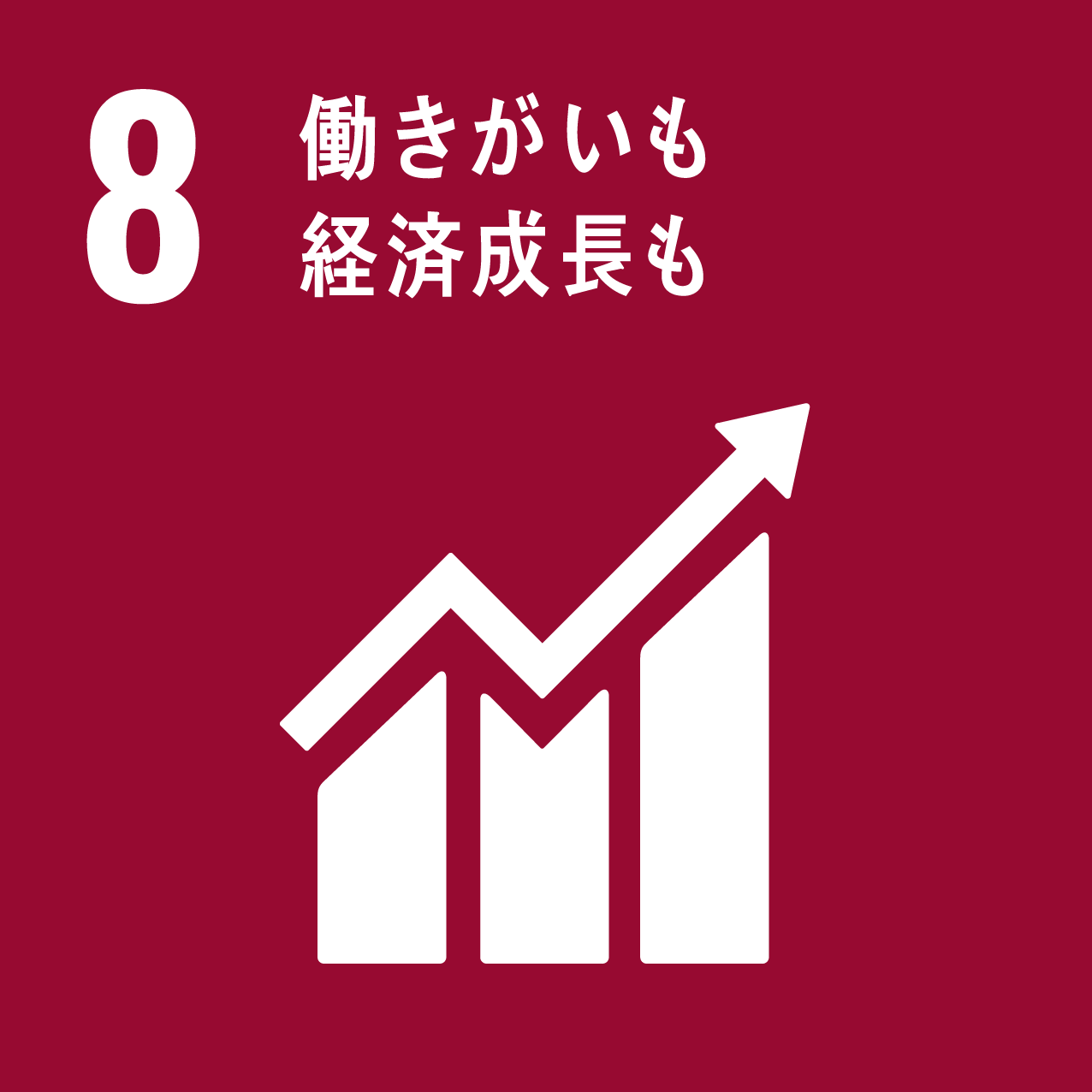




関連リンク
