少子高齢化に、未婚率・非婚率の高止まり、そして単身世帯の増加とともに、私たちが暮らす地域のつながりは、さまざまな原因で希薄になってきています。その一方、数多くのNPOやボランティア団体が、住民のwell beingをめざして、精力的に取り組み始めているのも事実です。地域社会に人々の居場所を取り戻すことをめざしたその活動は、「誰一人取り残さない」というSDGsの理想とも重なります。本学の「市民活動サポートプログラム」を受講し、地域づくりの最前線で活動している皆さんに、市民活動の今についてうかがいました。
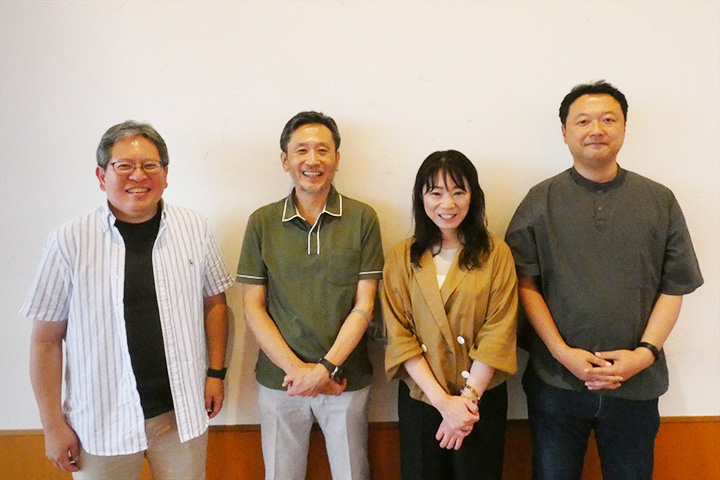
荒 裕二さん「特定非営利活動法人・市川市にJリーグクラブをつくる会」代表理事(写真右)
浅田由香さん「いちかわ子育てネットワーク」所属(写真中央右)
飯塚 学さん 我孫子市在住。自治会や町づくりイベントなどで活動中(写真左)
[ファシリテーター]
榎戸敬介 千葉商科大学 地域連携推進センター長、政策情報学部教授(写真中央左)
榎戸教授:まず最初に、皆さんが取り組んでおられる活動について教えてください。
荒さん:私は市川市に住んでいるのですが、地域コミュニティや地域ブランド力の希薄さ、地域経済の課題などが気になっていました。それでスポーツを通じて少しでもその解決ができればと、「特定非営利活動法人・市川市にJリーグクラブをつくる会」を立ち上げました。
現在、スポーツによるまちづくりを目指し、市川市からJリーグ入りを目指している社会人チーム「市川サッカークラブ」のサポートとして、選手たちが地元企業で働く環境を整えたり、スポンサー企業を募ったりと、町を巻き込んでのバックアップ活動に取り組んでいます。
浅田さん:私は「いちかわ子育てネットワーク」というNPO法人に所属しています。かつて自分が子育てをしていたとき、仕事を辞めて社会との接点が減り、孤立感に悩んだことがきっかけです。子育て世代と社会をつなぐ場がつくれたらいいなという思いで、活動を続けています。
飯塚さん:私の活動のはじまりは自治会です。私の住む地域は高齢化率が高く、たまたま持ち回りで役員をしていたとき、自治会の仕事が一部の人に集中し、大きな負担になっていることに気づきました。
幅広い世代が少しずつ仕事を分担し、できる範囲で協力し合えないかと考えるようになったことが活動の原点で、今は「コミュニティ/コーピング」(※)という、高齢者の社会的孤立やその解消を疑似的に体験できるゲームを通じて、地元の人たちと地域の課題を考える活動や町づくりにつながるイベントを参画をしています。
※コミュニティ/コーピング:一般社団法人コレカラ・サポートが、企画・開発を行ったボードゲーム。人と地域資源をつなげることで、超高齢社会の「社会的孤立」を解消するという協力型ゲーム。
地域づくりに求められる、温かいけれど軽やかな人間関係
榎戸教授:子育て世代も高齢者も、地域のなかで孤独を抱えていますね。仕事を引退した男性なども、人ごとではないでしょう。
飯塚さん:そうなんです。だから家庭と職場に次ぐ第三の居場所が、地域にあってもいいんじゃないかと思うのです。仕事がある人も、家庭中心の人も、みんなが少しずつ地域参加できればいいねというイメージです。
榎戸教授:いわゆるサード・プレイスですよね。北米などでは、人々の出会いの場や居場所としての役割を、教会が担っていることもあります。
荒さん:市川市の行徳に本久寺さんというお寺があって、8のつく土日祝日には、境内にキッチンカーが何台か来るんです。それを楽しみに人が集まるんですよ。
榎戸教授:おもしろいアイデアですね。寺社の境内は公共に近い場ですから、コミュニティづくりに活用できそうです。ただ、都会のコミュニティでは、ウェットで重い関係より、軽やかな付き合いが好まれる傾向にあるんですよ。
浅田さん:それ、よくわかります。「市民活動サポートプログラム」の授業で、「全国アンケートをとる」という演習をしたことがあるんです。「定期開催のイベントと、不定期に開催するイベント、参加するならどっち?」というアンケートでした。
結果はほぼ拮抗していました。友だちができるから定期開催がいいという人もいましたが、人間関係を気にせず参加できるという理由で、不定期開催を選ぶ人も同じくらいいたのです。そうした軽やかなつながりが、求められているのだなと実感しました。
町づくりの主役は住民。地域への誇りや思いが町を育てる
榎戸教授:冒頭で荒さんから、地域のブランド力という話が出ましたよね。もう少し聞かせていただけますか?
荒さん:私がスポーツを通じて市川市のブランド力を向上させたいと思った理由は、それによって住民のなかに、誇りやアイデンティティーが生まれると考えたからです。「市川市といえばコレ!」と誇れるものがあれば、みんなが自分の町にもっと注目し、町が好きになったり、自慢したくなったりするでしょう。地域の課題や魅力の発見や、選挙の投票率アップにもつながるかもと期待がふくらみます。
榎戸教授:ある町では、観光客が増えたことで、町がきれいになったといいます。ゴミが落ちていればすぐ拾い、家々の庭先にも花が増えたりしてね。注目されることで、町がきれいになったのです。
浅田さん:女優さんみたいですね(笑)
飯塚さん:やはり住んでいる人たちが主役なんですよね。自分の町がどうあってほしいのか、そのために、自分はどう関わっていくのか。行政任せ、他人任せではなく、住んでいる人たちの自覚や主体性が、町をよくしていくのでしょうね。
自信がない? 考えすぎ? 最初の一歩が踏み出せない理由
榎戸教授:地域のなかでやってみたい活動があっても、実行できない人は少なくありません。なかなか思い切れない最初の一歩を、皆さんはなぜ踏み出せたのでしょう?
飯塚さん:きっかけとなる「場」を見つけられたからだと思います。例えば自治会の役員などは、最初は順番で仕方なく引き受ける人が多いのではないでしょうか。でもそれをきっかけに主体的に動いてみると、いろんな刺激があって、いろんな人とも知り合って、少しずつおもしろくなってくる。どんな活動にも、そういう面があるのではないでしょうか。
浅田さん:子育て中のママたちのなかにも、やりたいことがあるのに躊躇している人は、おおぜいいます。皆さん、すごくまじめなんですよ。動き出す前からあれこれ心配して、周囲に迷惑をかける可能性が1パーセントでもあると、そこで諦めてしまう。
榎戸教授:そういう場合、浅田さんたちがサポートすることもあるのですか?
浅田さん:私が個人的に開催していた子育てママ応援サークルでは、こんなワークショップをやってみたいとか、やりたいことがはっきりしている場合は、会場の確保から、告知、集客、当日のサポートや託児までを引き受けていました。それでも子どもさんが熱を出して、当日ドタキャンということもありましたが、その場合は私が代行して参加者が別メニューでも楽しんでもらえるようにしていました。
見切り発車でもとにかく動いてみると、周りの人たちが助けてくれるものなのです。初心者にこそ、小さな迷惑をかけてもしかたがないという割り切りが、必要ではないでしょうか。思い切って踏み出したことで、ベビーマッサージの講師になったり、お教室を開いたりする子育てママたちが、実際にいるのですから。
榎戸教授:自分はこれをやりたいんだと、もっと発信することも必要ですよね。
浅田さん:ええ、「ネイリストの資格をもっているの」と話すうちに、「じゃあ私にやって」、「友だちを紹介するよ」と、身近なところから活動が広がっていくんです。
飯塚さん:深刻に考えすぎず、単純に「おもしろそうだな」と思って入っていくのが、私のパターンです。やりたい人がやりたいときに、やりたいことをおもしろがってやる。参加できないときは休めばいい。そのくらい気楽でいいと思うのです。
荒さん:同感です。私はよく周りから「大変ですね」と言われますが、べつに嫌なことをしているわけでも、無理にがんばっているわけでもないんですよね。好きだからやっているだけで、楽しいから続いているんです。
「CUC市民活動サポートプログラム」を受講して
榎戸教授:最後に、「CUC市民活動サポートプログラム」を受講した感想をうかがいましょうか。
飯塚さん:大学の授業だけあって、地域活動・市民活動に関して、体系的に学べた点がとてもよかったです。日頃の活動や生活圏を離れ、もう一度学生に戻って学ぶ楽しさも満喫しましたよ。
浅田さん:フィールドワークや演習を通した、実践的な学習がすごく新鮮で、もちろん自分の活動にも応用することができました。私は我流でやっていた活動を見直したくて受講したのですが、思った以上に勉強になったと感じています。
荒さん:私は受講中にNPOを立ち上げたので、学んだすべてがオンタイムで役立ちました。授業に加え、同期の受講者の皆さんからも刺激を受け、視野を広げられたことが大きな収穫です。
榎戸教授:ありがとうございます。プログラムは終了しましたが、皆さんどうぞ、今後もますますご活躍ください。
この記事に関するSDGs(持続可能な開発目標)


関連リンク
