——自由で明るい市場主義の時代が続いたがーー
ちょうど30年前の1993年、わたしたちは『日本経済フェアプレー宣言』(香西泰・内田茂男編著:日本経済新聞社)で、「1993年は『戦後』という歴史に終止符を打ち、新しい時代の幕開けを告げた記念碑的な意味合いをもった年になるに違いない」という時代認識を提示しました。

『日本経済フェアプレー宣言』香西泰・内田茂男編著(日本経済新聞社1993年刊)
そのように考えた背景は大きく2つありました。第1は、「世界が一つになった」という空気が一気に広がったことです。1991年12月にソ連が崩壊し、ソ連圏諸国がわたしたちと同じ市場経済圏に仲間入りしました。東西冷戦が終わり、核戦争の脅威から世界が解放されたことも大きなインパクトになったと思います。さらに1989年6月の天安門事件で世界から経済制裁を受けていた中国が、1992年初めの鄧小平の「南巡講話」(中国共産党の指導者だった鄧小平が上海など中国南部を巡回し、改革・開放を説いて回ったこと)をきっかけに、経済活動に市場経済の要素を大幅に取り入れました。こうして「世界は一つ」「世界は一つの市場」という雰囲気が世界に浸透していったのです。
第2は、鉄鋼からハイテク製品までの製造業のほとんどの分野で世界市場を席捲していた日本企業の経営のありかた(「日本的経営」)や日本の輸出主導型経済成長に対し、欧米諸国から批判の声が強まったことです。この点は前回、ソニーの盛田昭夫会長(当時)が『文芸春秋』1992年2月号に書いた論文、「日本的経営が危ない」を引用して説明しておきました。
昨年2月、ロシアがウクライナを武力によって一方的に侵略を開始しました。これによって「世界は一つ」の時代は終わったといえるかもしれません。再び世界は、2つに分かれようとしているようにも見えます。核の脅威も再び意識されるようになってきました。30年前に戻ったようにみえます。
ただ、いままでの30年は、わたしたちが期待したように、自由民主主義と市場経済が世界をリードした明るい時代だったといえるのではないしょうか。この時代を十分過ぎるほど享受したのは中国です。中国は、2001年にWTO(世界貿易機関)へ加入して以来、高速成長を続け、2010年にはGDP(国内総生産)で日本を抜いて世界第2の経済大国になりました。
製造業の競争力が強大過ぎると欧米諸国から冷たい目でみられていた日本の姿は、その後、わたしたちの予想を完全に裏切り、「失われたに30年」といわれるような暗いトンネルに入り込んだままで現在にいたっています。なぜでしょうか。
——「複合不況」の本質を見誤った
反省を込めて30年前を振り返りますと、政治も行政も産業界も、加えてジャーナリズムも学会も、日本国民のほとんどすべてが、バブルの生成、崩壊の性格と影響の甚大さを見誤ったのです。この誤診が日本の経済力を弱体化させ、このことがその後の長期停滞をもたらしたのだと考えます。
保守本流の本格政権と言われた宮澤喜一内閣が1992年6月に閣議決定した経済計画「生活大国5か年計画—地球社会との共存をめざして」が最初のつまづきでした。筆者もこの計画策定に経済審議会委員として参加していたのですが、90年の年初から株価や地価が急落を続けていたにもかかわらず、会議の雰囲気は終始、楽観的でした。市場の混乱を深刻に受け止める議論は皆無だったと記憶しています。
それを象徴するのは計画期間(92~96年度)の想定実質成長率を年率平均で3.5%に設定したことです。バブル時代を90年度までの5年間とすると、この間の実質成長率は4.9%(年率平均)でした。新しい経済計画は、それよりやや低めの成長率を設定したのですが、計画の理念がそれまでの輸出主導型成長から国民生活の充実を目指した内需主導型成長への転換にあるのだから、成長目標は抑え気味にすべきだ、という理屈だったと思います。筆者はこの点を審議するマクロ部会に所属していたのですが、3.5%の事務局案は消極的に過ぎるとして、3.75%を主張しました。実際はゼロ成長(年率0.05%)だったのです。前回ふれたようにその後の30年を通じて平均成長率は1%に届いていないのです。
不明を恥じるばかりですが、当時の雰囲気はこんな感じでした。大蔵省(現財務省)の幹部と議論した際、株価の急落が景気悪化につながる気配があるから景気対策を準備すべきだとする筆者の考え方に、彼は「株価が下がっても困るのはお金持ちだけではないですか。景気対策など必要ありませんよ」といったのです。
記憶にとどめておきたいのは、1992年6月に横浜国立大学の宮崎義一教授が「複合不況—ポスト・バブルの処方箋を求めて」(中公新書)を著し、バブル崩壊後の不況は、それまでのような有効需要不足による循環的な景気後退ではなく、金融自由化による過剰流動性が引き起こした土地などの過剰ストックの調整による新型不況だと論じていました。いまで思えば実に的確に分析していたのです。ところがほとんどの関係者が関心を示しませんでした。実際、1992年夏、株価の暴落に宮澤首相があわてて避暑地の軽井沢から帰って、株価対策を含む大型の総合経済対策を決めたのですが、基本的には従来型の有効需要政策の域を出ないものでした。
新型不況の恐ろしさの一端が垣間見えたのは、「住専問題」でした。「住専」というのはバブル期にほとんどの大手銀行が設立したノンバンク(預金を預からない金融機関)で親会社の銀行からの借り入れを原資に中小企業の住宅・土地関連融資や個人向け住宅ローンなどを専門に行っていました。いわば銀行の隠れ蓑だったのです。
この住専が地価の暴落で一気に経営難に陥ったのです。住専からの借入金で住宅・不動産投資を行っていた融資先の多くが地価の暴落で借入金の返済ができなくなったからです。結局、住専7社全社を破綻させることになったのですが、貸し手の銀行に債権放棄をさせたうえで、残った破綻処理資金6,850億円を1996年度政府予算に計上することで決着しました。
問題は定期的に住専の経営状況を調査していた大蔵省が、住専の不良債権問題の深刻さを把握しながら、情報を公開せず対応を遅らせたことです。その結果、国民の税金をつぎ込まざるを得ないまでに傷を大きくしてしまいました。地価はやがて戻るという無責任な先送り主義に陥っていたのです。こうして、「住専経営失敗のつけをどうして国民が払わなければならないのか」という政府非難の声が高まりました。筆者もそのような社説を書きました。このことがさらに巨大な大手銀行の不良債権問題への行政の対応を遅らせることにつながったのです。

銀行の「不良債権」の始末に15年
住専問題をきっかけに大手銀行が巨額な不良債権を抱え、身動きが取れなくなってきていることが次第に明らかになってきました。政府資金(公的資金)をつぎこむことになっても、できるだけ早期に不良債権問題にケリをつけるべきだったのですが、住専問題の処理で不評を買った行政の対応は大きく遅れました。この間、不良債権を大量に抱えた銀行は、貸し渋り(新規融資の抑制)や貸しはがし(融資した資金を無理やり返済させる)といった、銀行にあるまじき行動をとり、ただでさえ苦境にあえいでいた企業経営を圧迫したのです。
そうこうしているうちに97年11月に大手銀行の一角だった北海道拓殖銀行が破綻しました。翌年には日本長期信用銀行、日本債権信用銀行が相次いで行き詰まり、国有化される事態となりました。こうして日本の銀行や金融システムへの国際的評価はガタ落ちとなったのです。当時はアジア通貨危機の真っただ中で、筆者はIMF(国際通貨基金)管理下に入った韓国、タイ、インドネシアを訪問取材していたのですが、その帰国便で秀才が集まっていた名門、日本長期信用銀行(長銀)破綻のニュースに接しました。「日本もか!」と暗澹とした気持ちになったことを鮮明に思い出します。ルピアの暴落で急激なインフレに見舞われていたジャカルタでは中国人街がひんぱんに焼き討ちされている状況で、予約していたホテルに日本大使館から「外出自粛」の通達が届けられていました。
大手銀行の不良債権問題が公的に片付いたと判定されたのは2005年4月です。ペイオフが全面的に解禁されたのです。ペイオフというのは銀行が倒産しても一定限度の預金(現在は最大、預金を合算して1人1,000万円プラス利息)を保障するという仕組みのことで、96年6月の預金保険法改正で凍結されていたのです。つまりこの間に銀行が倒産しても全預金が保護されることになっていたのです。というのもそれまで銀行が破綻することは事実上なかったので、仮にそのような事態が発生してペイオフが実施されれば金融システムへの信頼が一気に崩壊する恐れがあったからです。この間、金融再生法の制定など大手銀行が破綻しても対応できるように法的体制が整えられました。こうした仕組みの上で大手銀行へ巨額の公的資金が投入され、同時に都市銀行は大幅に整理されました。日本興業銀行、富士銀行、第一勧業銀行がひとつになって「みずほ銀行」になったのはその典型例でしょう。
こうして日本経済を根底から揺さぶった銀行の不良債権問題に終止符が打たれたのは、バブル崩壊によって問題が発生してから実に15年も経ってからです。
一方、バブル期に積極的に借り入れを行って設備投資、不動産投資に走った企業は、いわゆる3つの過剰(過剰な負債、過剰設備、過剰人員)の始末に追われました。財務省「法人企業年報」によりますと、1995年前後の企業の負債額はバブルが始まった1985年に比べ製造業で1.6倍、非製造業で2.3倍にふくらんでいました。また日銀「短期経済観測」でみますと民間企業の生産設備・営業用設備の過剰が解消するのは2005年になってからです。
民間企業も銀行と同様に正常の姿に戻るのに15年を要したのです。この結果、急激に進んだ情報技術革新への対応に遅れをとり、「一つの世界」で進展したグローバリゼーション時代の波に完全に乗り損ねました。

潮目は変わったー日本経済復活の気配
しかし、ここに来て潮目は大きく変わったように思います。そう見る理由は大きく3つあります。第1に、「生活大国5か年計画」で目指した内需主導型成長は30年経っても実現しませんでしたが、ようやく内需の柱である国民の消費や企業の設備投資が増加基調に転じる気配が見えてきました。
政府の「新しい資本主義実現会議」が昨年末に公表した資料によりますと、2019年までの30年間で日本の勤労者の実質賃金はわずか5%しか増えていません。ゼロ成長です。この間に、イギリスが48%、アメリカが41%、ドイツ、フランスが34%も上昇しているのと大違いです。企業が、「この30年」の前半15年は過剰雇用に悩まされ、その後も成長軌道に乗れなかったことがその1つの理由ですが、もう1つの大きな理由は、昨年当欄で指摘しましたように、企業が、急成長を続けていた中国に生産拠点を移したことでした。日本の労働力は減少し続けていますが、企業は中国で労働力を調達したのです。したがって日本で賃金を上げる必要はなかったのです。
ここで指摘しておく必要があるのは、日本の労働者の生産性は上昇していたことです。ダボス会議の主催者であるK・シュワブ教授らは、近著「グレート・ナラティブ 「グレート・リセット」後の物語」(日経ナショナル ジオグラフィック 2022年)で「(日本の)2007年以降の生産年齢人口1人当たりの実質GDPはG7(主要7カ国)のどの国よりも伸び率が高い」と高く評価しています。筆者も確かめてみましたが、その通りでした。それでも賃金が上がらなかったのは、日本企業が中国で労働力を確保したため、日本の労働市場がタイトにならなかったからです。
しかし、その中国も2013年をピークに生産年齢人口が減り始めています。労働力の供給源としての中国の存在感は減退せざるをえません。一方で日本の労働力は大きく減ってきていますから、賃金は上がらざるをえません。実際、ことしの春闘の賃上げ率は3%を大きく上回り、ほとんど30年ぶりの高さでした。
第2に、企業の設備投資が上向き始めたことです。日本経済新聞社などの調査では今年度の設備投資は全産業ベースで本当に久しぶりに2ケタで増える見通しです。日本企業はこれまで中国を中心に海外への投資に力を入れてきましたが、経済安全保障の観点から国内回帰を目指す動きも活発になってきています。投資資金も準備されているとみていいでしょう。内閣官房の公表データによりますと、2000年度から2020年度にかけて大企業の人件費は0.4%減少しましたが、蓄積された現預金は85%、経常利益は91%増加したということです。
第3は、深刻化する気候変動への対応が本格化するのはこれからで、情報技術革命では後れを取った日本企業にもチャンスが大いにあるということです。IEA(国際エネルギー機関)は、2050年度までに二酸化炭素の実質排出量をゼロにする「パリ協定」を成功させるためには8,000兆円の資金が必要だとしています。この分野には壮大なマーケットがあるわけで、各国企業が新技術開発にしのぎをけずっているところです。主要国は軒並み政府が補助金や融資を通じて大規模な企業支援策に乗り出していますが、わが岸田政権も「社会的課題をエネルギーとして新たな成長を図る」という方針を明確に打ち出しています。産業革命以来の大技術革命だといわれるGX(Green Transformation)は日本企業にとって成長への大きなチャンスとみるべきでしょう。
以上、「失われた30年」は終幕を迎える、というのがわたしの見方です。すこし長くなりましたが、(上)を振り返りながら考えてみました。

内田茂男(うちだ・しげお)
1965年慶應義塾大学経済学部卒業。日本経済新聞社入社。編集局証券部、日本経済研究センター、東京本社証券部長、論説委員等を経て、2000年千葉商科大学教授就任。2011年より学校法人千葉学園常務理事(2019年5月まで)。千葉商科大学名誉教授。経済審議会、証券取引審議会、総合エネルギー調査会等の委員を歴任。趣味はコーラス。
<主な著書>
『ゼミナール 日本経済入門』(共著、日本経済新聞社)、『昭和経済史(下)』(共著、日本経済新聞社)、『新生・日本経済』(共著、日本経済新聞社)、『日本証券史3』、『これで納得!日本経済のしくみ』(単著、日本経済新聞社)、『新・日本経済入門』』(共著、日本経済新聞出版社) ほか
この記事に関するSDGs(持続可能な開発目標)
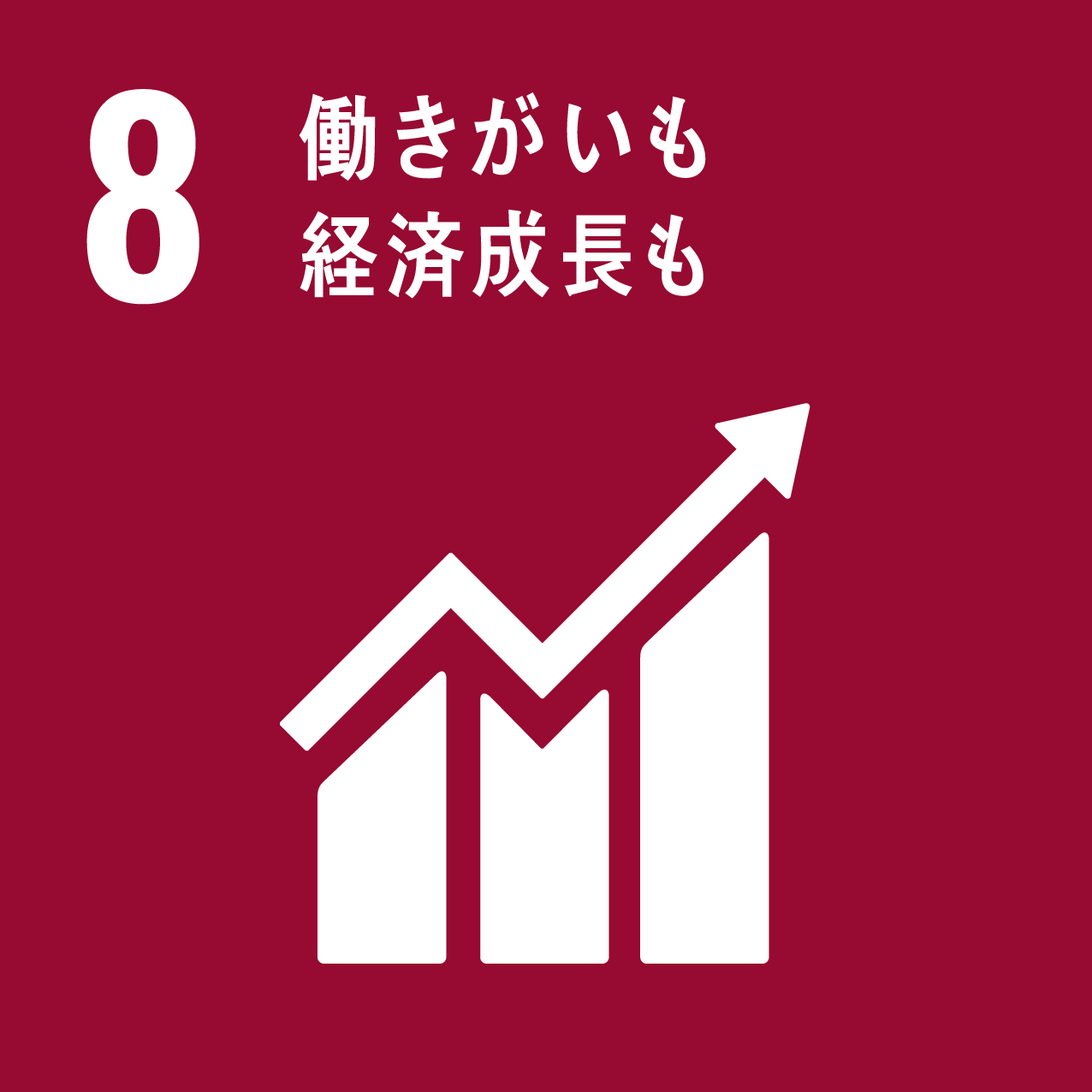

関連リンク
